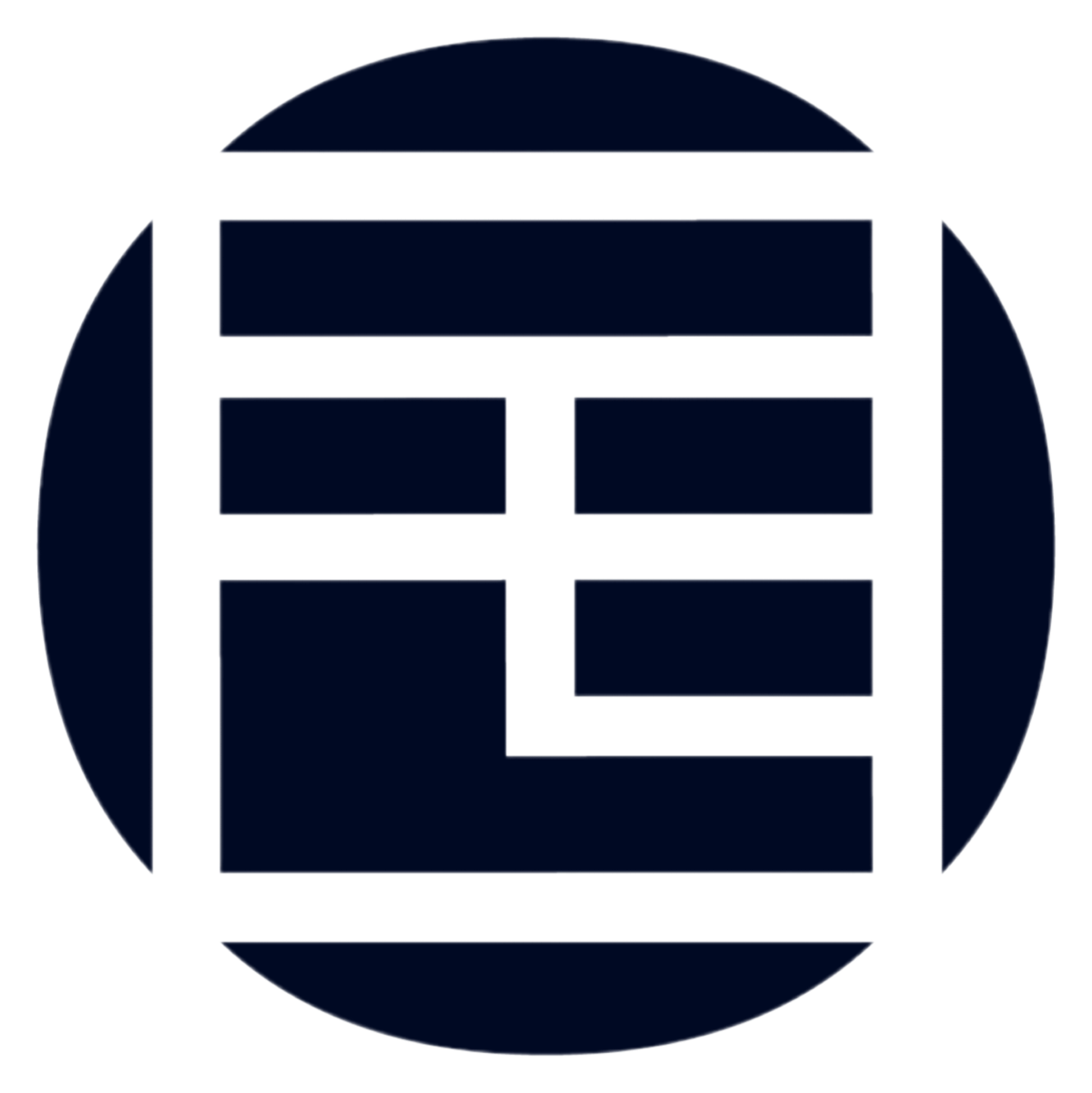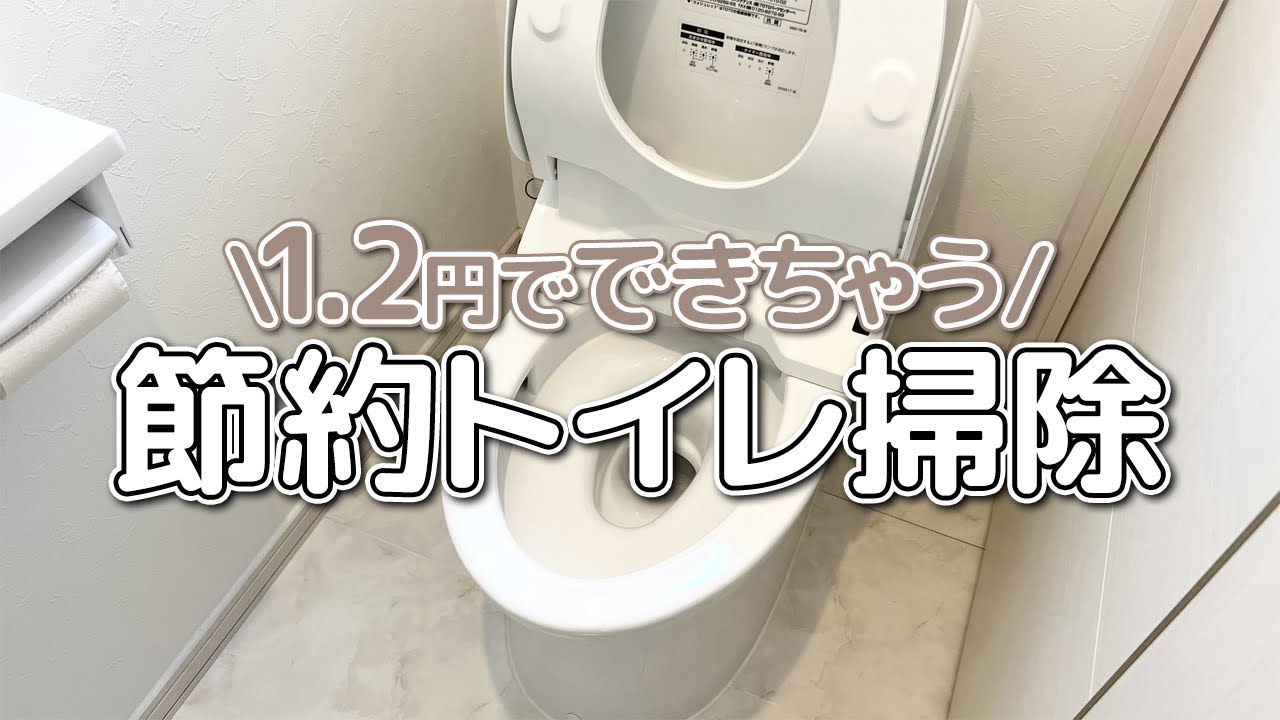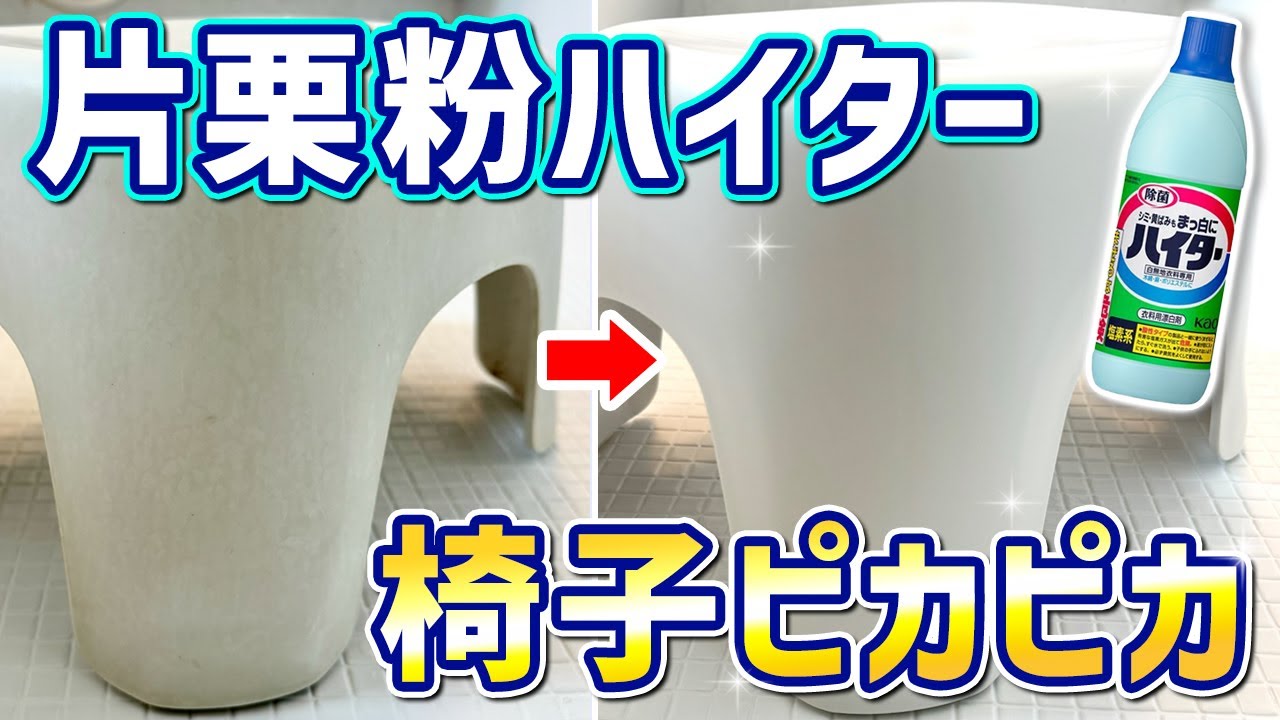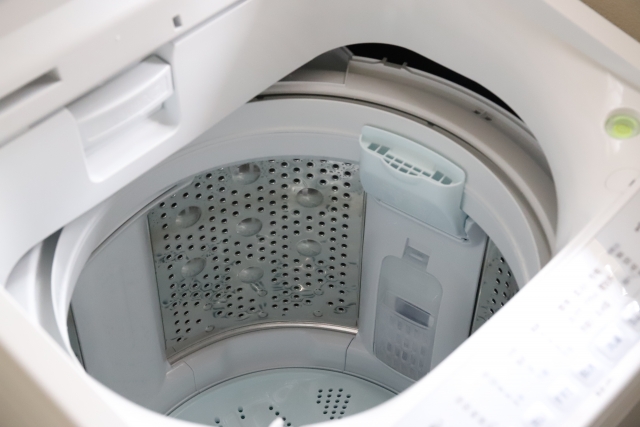フライパンのコゲは落ちる?セスキ炭酸ソーダの限界と活用術を徹底検証!

60秒で読める!AI記事要約
セスキ炭酸ソーダでフライパンのコゲは落ちる?徹底検証!
セスキ炭酸ソーダは油汚れに強いですが、フライパンの頑固なコゲ付きには限界があることが検証で判明しました。
セスキ炭酸ソーダ水、ジェル、ホットセスキ炭酸ソーダの3つの方法でコゲ落としを試しました。
▼コゲ落とし検証結果
◎セスキ炭酸ソーダ水(水100mLに1g)
コゲに塗り、ティッシュで30分ペーパー湿布。
結果: コゲは落ちず、油汚れまでが限界。
◎セスキ炭酸ソーダジェル(セスキ水約20gに片栗粉1gを加熱)
コゲに塗布し、食器用洗剤を混ぜて30分放置。
結果: 多少効果はあるが、劇的には落ちない。研磨スポンジ併用で多少落ちる程度。加熱でpHが下がる可能性も。
◎ホットセスキ炭酸ソーダ(加熱したセスキ水+食器用洗剤)
コゲに塗布し、ペーパー湿布で30分放置。
結果: 劇的な変化はなく、ガンコなコゲには力不足。pHは加熱前後でほぼ変化なし。
▼結論とおすすめの使い方
頑固なコゲ: セスキ炭酸ソーダは、高温で長期間放置されたガンコなコゲには不向きです。完全にピカピカにするのは難しい結果となりました。

こんにちは!のぞみです。
今回はフライパンの裏についたコゲ付き汚れを、セスキ炭酸ソーダで落とす方法をあれこれ試してみようと思います。
セスキ炭酸ソーダの洗浄力を高める2つの方法も試しているので、ぜひ最後までご覧くださいね!
ちなみに今回参考にしたのは、こちらの茂木和哉(@motegikazuya)さんのYouTube動画です!
「セスキ炭酸ソーダ」でコゲ落とし準備編♪
まずは「セスキ炭酸ソーダ」を使って、洗浄液を作っていきましょう。
セスキ炭酸ソーダは、レンジ周りやグリルの油汚れ、換気扇の汚れ落としなどに使える頼れるお掃除アイテム。今回はその使い方をちょっぴりアレンジして、コゲ落としに活用してみます♪
パッケージの「レンジまわりやグリルの油汚れ、換気扇の汚れ落とし」のところを参考にします。
「水500mLに対して5グラム」と書かれているので、基本は100倍の希釈ですね。
今回はそれほど大量には使わないので、水100mLにセスキ炭酸ソーダを1グラム加えていきます。
キッチンスケールにお掃除用マグカップをセットして、セスキ炭酸ソーダを1グラムいれたら、水を100mL注ぎます。ここはざっくりで大丈夫ですよ~♪
今回は純粋なセスキ炭酸ソーダの洗浄力をみたいので、お湯ではなく水で溶かしてみます。
油汚れやコゲはお湯のほうが汚れ落ちは良くなるので、実際にお掃除に使うときはお湯を使うのをおすすめします!
よくかき混ぜたら、セスキ炭酸ソーダ水の完成です。
セスキ炭酸ソーダはアルカリの力で汚れを分解してくれるのですが……気になるのはそのアルカリ度。
ということでpHを測ってみたところ、今回はpH9.76という結果に。しっかりアルカリ性ですね!
このくらいのpHがあれば、油汚れや軽いコゲは落としてくれそうな気がします〜!
セスキ炭酸ソーダでコゲ落とし!どこまで落ちる?
セスキ炭酸ソーダ洗浄液を塗りつける
作ったセスキ炭酸ソーダの洗浄液を、コゲついた鍋の裏に塗りつけていきます。
セスキ炭酸ソーダはアルカリの力で油汚れを落としてくれるのですが……実は界面活性剤が入っていないんですよね。
なので塗り付けたとき、弾かれやすいという弱点があります。
なので、液をぺたっと乗せるというよりは、少し盛り上がるくらいしっかりめに塗りつけるのがポイントです!
ちなみにここで「食器用洗剤」をほんの少し加えると、界面活性剤のはたらきで洗浄液が垂れにくくはじかれにくくなるというメリットがあります。
セスキ炭酸ソーダの浸透力がぐっと高まりますし、洗浄力をアップさせるなら、混ぜて使ってみましょう。
まずは純粋なセスキ炭酸ソーダの力だけを見たいので……ここでは食器用洗剤を混ぜずに使っていきます。
洗浄液を塗り終えたら、上からティッシュをかぶせてペーパー湿布をしていきます。
こうすることで、洗浄液が流れ落ちにくくなり、コゲの部分にしっかりとどまってくれます。
食器用洗剤を混ぜず、セスキ炭酸ソーダだけで使うのならぜひペーパー湿布をしておきましょう~!
この状態で、約30分ほど放置してみますよ。
30分放置すると?
セスキ炭酸ソーダの洗浄液を塗り付けてから30分が経ちました!
しっかりペーパー湿布もしましたので、液が垂れてしまうことなく、コゲの部分にちゃんととどまってくれていましたよ♪
……が、いざブラシでこすってみても、残念ながらコゲは落ちていきません。
どうやら、セスキ炭酸ソーダで落とせるのは、あくまで油汚れまでのようですね。
コゲのようにしっかりとこびりついてしまった汚れには、ちょっと力不足だったようです……。
セスキ炭酸ソーダジェルでコゲ落とし
セスキ炭酸ソーダ水ではちょっと力不足だったので、次はジェル状のセスキ炭酸ソーダで再チャレンジしてみます!
粘度を高めることで、コゲ部分にしっかり密着させる……という作戦です。
余ったセスキ炭酸ソーダ水(約20グラム)に「片栗粉」を1グラム加えて、小鍋で弱火にかけながらとろみをつけていきます。
混ぜているうちに、だんだんとジェル状に変化!とろっとした質感になったらOKです♪
このセスキ炭酸ソーダジェルを、コゲた鍋の裏にたっぷり塗りつけていきます。
ジェルなので液ダレの心配がなく、ペーパー湿布なしでもしっかり留まってくれるのがいいところ♪
そしてここで、ちょっと工夫を……。
「食器用洗剤」を少しだけ混ぜてみましょう!界面活性剤の力で、セスキ炭酸ソーダの浸透性がアップしてくれますよ〜。
塗りつけたあとは、歯ブラシで軽くこすってみます。
セスキジェルの温度が下がってくると、ジェルの色が少し変化してきました。どうやら食器用洗剤と反応しているようですね。
お鍋全体に塗り広げたら、そのままの状態で30分放置してみます!
セスキ炭酸ソーダは加熱するとアルカリ度はかわる?
ところで、セスキ炭酸ソーダのアルカリ度(pH)は加熱するとどう変わるのでしょう?
重曹は加熱するとpHが上がり、アルカリ性が強くなることで知られています。
加熱したセスキ炭酸ソーダのpHを測定してみると……なんとpHは9.36にダウン。
加熱前はpH9.76でしたからね。アルカリ度が下がって中性に近づいてしまいました。
おそらく「食器用洗剤」を加えたことで、何らかの化学的反応が起こったのかもしれません。
正直アルカリ度が下がってしまうと、コゲ落ちはあまり期待できない気もしますが……。
このあとまた、セスキ炭酸ソーダを加熱して使っていく予定なので、もう一度計測しておきましょう。
30分放置してみると
セスキジェルを塗り付けてから30分が経ちました。
ジェルのようすは食器用洗剤と混ざった部分は白っぽくにごり、混ざらなかった部分は透明のままですね。
見た目にもあきらかな違いが出ています。
歯ブラシで軽くこすってみると……劇的にコゲが落ちるというわけではないようです。
ただし水と混ぜただけのセスキ炭酸ソーダ洗浄液よりは、いくらか効果が見られる感じはありますね。
研磨スポンジでこすってみる
つぎはダイソーの研磨剤入り不織布スポンジを使ってみます。
使いやすい大きさにカットして、セスキ炭酸ソーダジェル+食器用洗剤+研磨スポンジの合わせ技でこすってみます!
結果はというと……多少は落ちますね。
ただし、「スルッと落ちる!」という感覚ではなく、ある程度こすらないと厳しいというのが正直なところです。
このままセスキジェルでコゲ取りをしていくのは、ちょっと難しい気がします。
セスキ炭酸ソーダジェルにコゲ落とし効果はある?
セスキ炭酸ソーダをジェル化し、熱や界面活性剤も加えることで多少の効果はありましたが……こびりついたコゲに対してはやはり限界があるという印象でした。
とはいえ、油汚れや軽めのコゲには効果あり!
ジェル状にすることで扱いやすさもアップするので、一番初めに試したセスキ炭酸ソーダを水を混ぜただけの洗浄液よりかは効果はありそうです。
ホットセスキ炭酸ソーダでコゲ落とし
セスキ炭酸ソーダ洗浄液、セスキジェルと試してきましたが……最後はホットセスキ炭酸ソーダを試していきます!
用意するのは、水とセスキ炭酸ソーダ、そして少量の「食器用洗剤」です。
今回は片栗粉などでとろみをつけず、そのまま加熱して洗浄力アップを狙います!
小鍋に入れてぐつぐつと煮立ってきたら、すかさず鍋の裏面へ塗りつけます。
垂れないようにペーパー湿布もしていきますね。
このとき、ペーパーの端は折り返すと液だれ防止にもなりますよ♪
気になるアルカリ度は?
放置しているあいだに、気になるアルカリ度を調べておきましょう。
セスキ炭酸ソーダを加熱したときのアルカリ度(pH)は……pH9.7となりました。
つまりセスキ炭酸ソーダは加熱前と加熱後でpHはほぼ変化がないようですね。
重曹は加熱するとpHがぐっと上がる性質があります。ですがセスキ炭酸ソーダはそれほど変化しません。
そう考えると加熱することでpHが変わり、あれこれアレンジもできる、重曹のほうが使いやすいのかも?と思いますね。
30分放置してみた結果は?
ホットセスキ炭酸ソーダでペーパー湿布してから30分が経ちました。
ペーパーを外して、研磨スポンジでこすってみると……うーん、少し落ちやすくなったような気もしますが、劇的な変化は見られません。
ガンコなコゲにはやはり手強いですね。
やっぱりセスキ炭酸ソーダを加熱したり、食器用洗剤を加えてみても、ガンコなコゲには限界があるようです。
ホットセスキ炭酸ソーダの効果はある?ない?
最後は「セスキ炭酸ソーダ+食器用洗剤+研磨剤入り不織布」の組み合わせで挑戦しました。
結果としては……多少はコゲが落ちるけど、スルッとはいかない、となりました。
セスキ炭酸ソーダはナチュラルで扱いやすく、油汚れなどにはとっても頼れる存在ですが、コゲのような強力な汚れにはちょっと苦戦しがちです。
加熱することで洗浄力アップを期待しましたが、pHは大きく変化せず、汚れ落ちも限定的という結果に。
ナチュラルクリーニングで無理なく落としたい場合には有効ですが……ガンコなコゲ落としとなると、使い方を考えないといけませんね。
研磨力のある専用クレンザーを使ったり、加熱してpHを高めた重曹のほうが効果的かもしれません。
あれこれ試した後のコゲのようすをチェック
最後にペーパータオルを外して、水ですすいできました。
全体的に見て、確かに最初のガンコな状態に比べるとかなりキレイにはなっています!
…………ですが、やはりまだ残っているコゲもありますね。
金属がヤケたような黒い部分は素材の性質上どうしても残ってしまうのですが、それ以外の茶色いコゲ汚れも部分的には残ってしまいました。
セスキ炭酸ソーダは、ナチュラルで安心して使えるお掃除アイテムですが、今回のように高温+長期間放置されたコゲ汚れとなると、なかなか手強かったですね。
「少しでもやわらかくして、落としやすくする」という意味では効果を感じましたが、完全にピカピカに!とはいかないというのが正直なところ。
ただ、軽めのコゲや日常的な油汚れには本当におすすめなので、普段のお手入れに上手に取り入れていきたいですね♪
今回のコゲ取り掃除を振り返って
セスキ炭酸ソーダでコゲが落としにくい
ということで今回は、フライパンの裏にこびりついたコゲ汚れを、セスキ炭酸ソーダで落とせるかどうか、いろいろ試してみました!
……が、正直なところ、劇的な効果は出ず、参考になるか微妙な内容だったかもしれません。
セスキ炭酸ソーダを加熱したり、片栗粉でジェル化してみたりと、洗浄力を高めるための工夫もいくつか試してみました。
結果としては「軽い汚れには多少効果あり、でもガンコなコゲには限界あり」となりましたね。
もっと手軽にコゲを落とすなら?
もっと手軽に、身近なものでコゲを落とすなら……まずおすすめはアルカリ電解水です。
アルカリ電解水もナチュラルクリーニング素材ですが、セスキ炭酸ソーダよりもアルカリ度が高いんですよね。
実は以前、アルカリ電解水を加熱してコゲ落としに挑戦したこともあるんです。
そのときは片栗粉を混ぜてジェル状にして使っていきました。
使い方が気になる方は、茂木さんのこちらの動画でチェックしてみてくださいね♪
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、フライパンの裏にこびりついたコゲ汚れを落とすために、セスキ炭酸ソーダを使っていろいろと試してみました。
正直なところ、セスキ炭酸ソーダはコゲ取りには向いていません。
それでも軽めの油汚れやキッチンまわりのベタつき掃除にはセスキ炭酸ソーダはとても優秀!
ナチュラルで安心して使えるので、普段使いのお掃除にはぴったりだと思いますよ~♪
また、YouTubeチャンネル「のぞみのお掃除講座」では、お掃除にまつわるいろんな情報をお届けしています。
こちらの動画もみてもらえると嬉しいです!
さらに自分にあったお掃除法を見つけたいという方は、「汚れ落とし研究家 茂木和哉のラクラク掃除術」を読んでみてくださいね。
茂木さんがお掃除ノウハウを、わかりやすくまとめてくれていますよ~!
それではここまで読んでくださり、ありがとうございました。
またお会いしましょう~♪